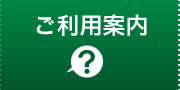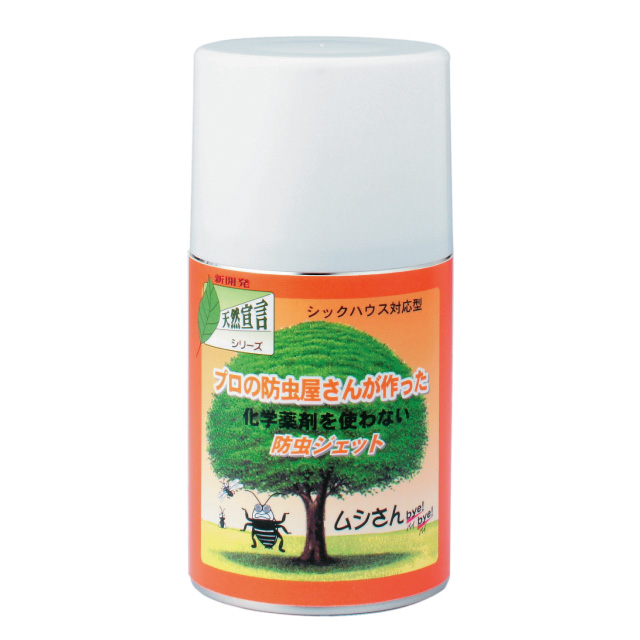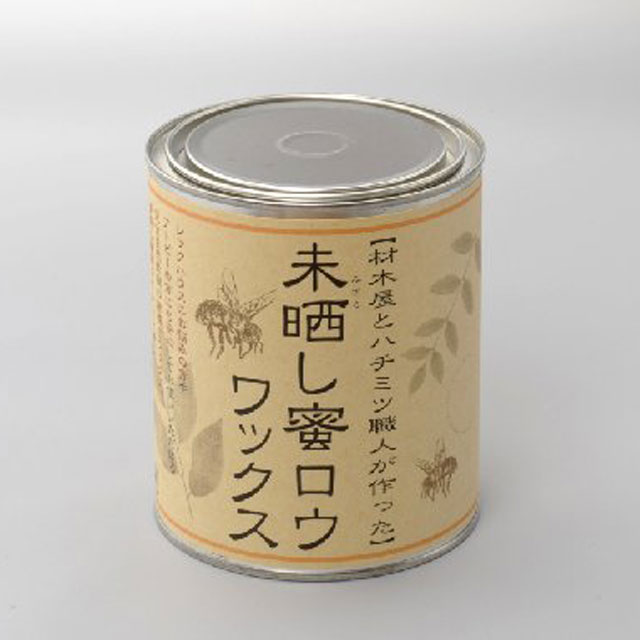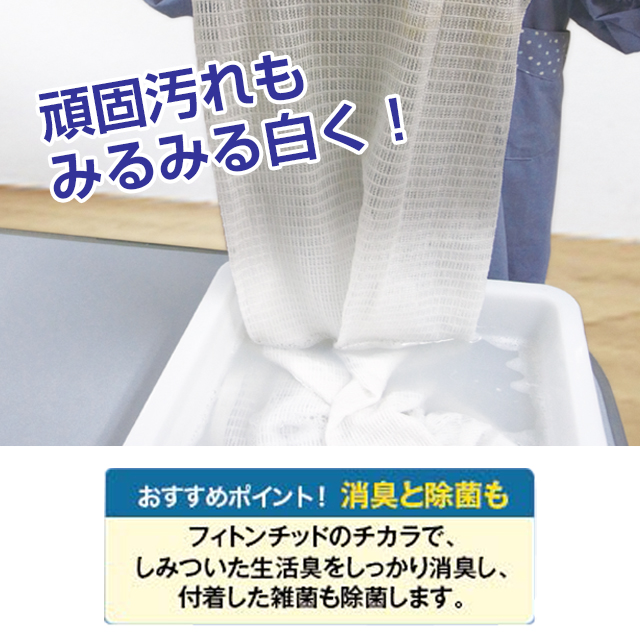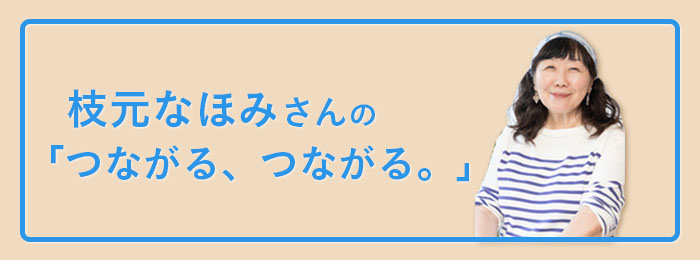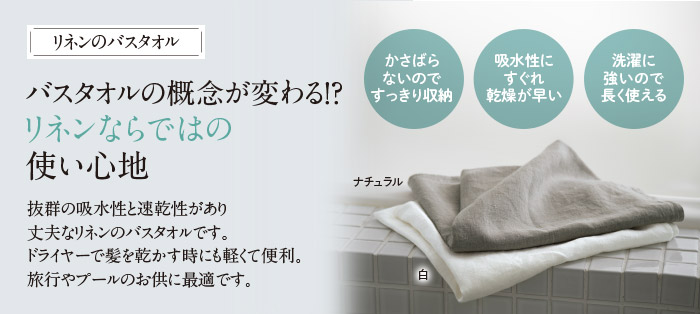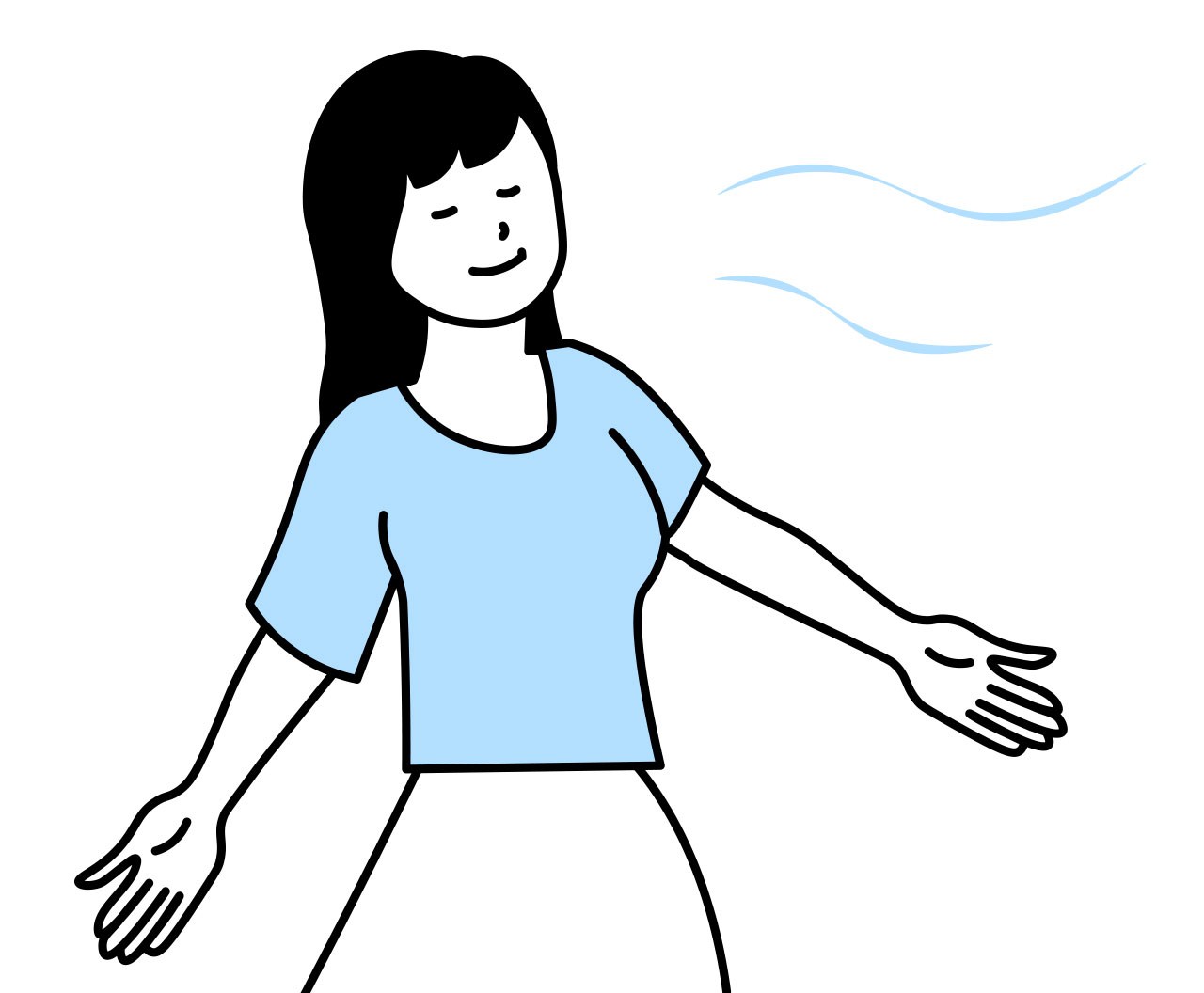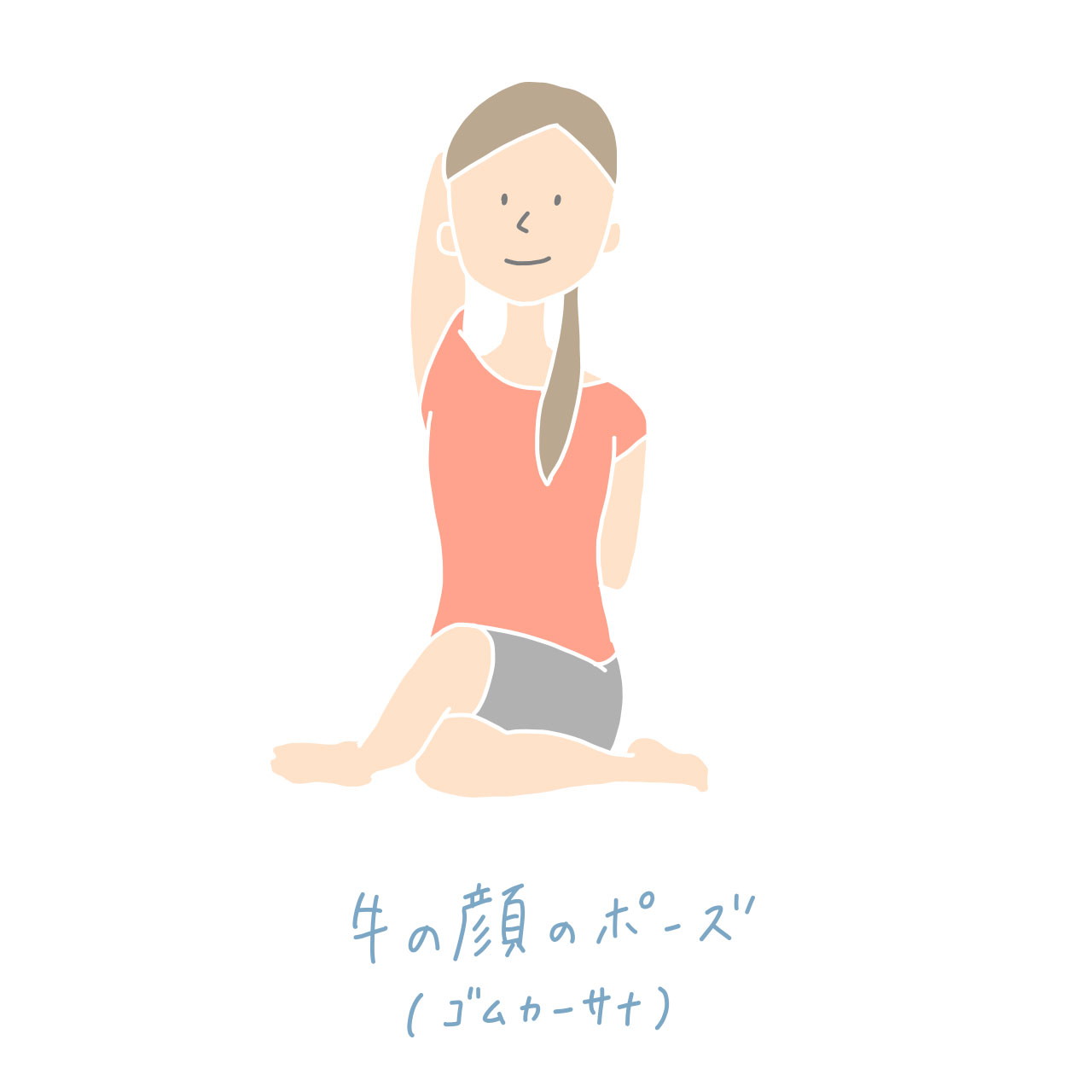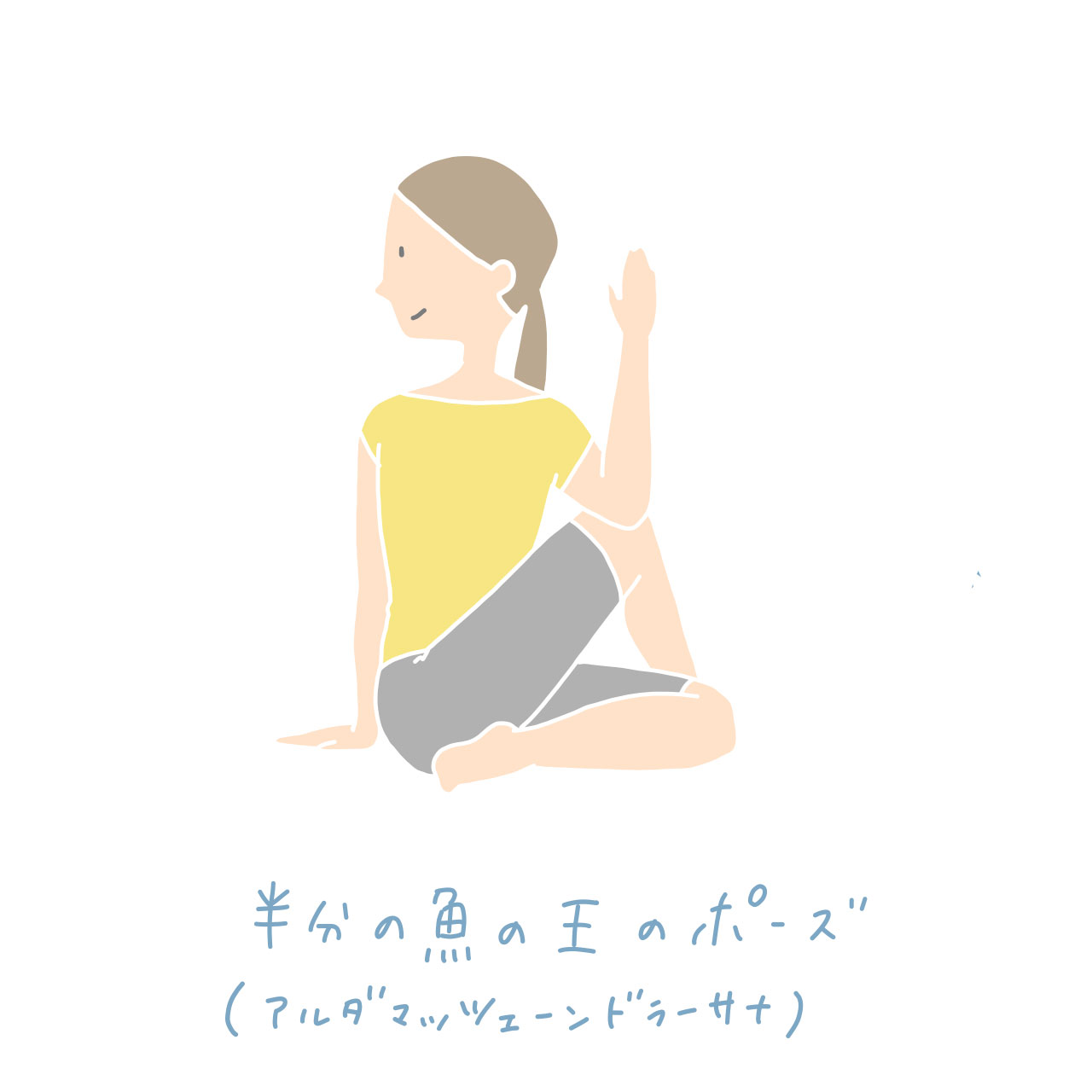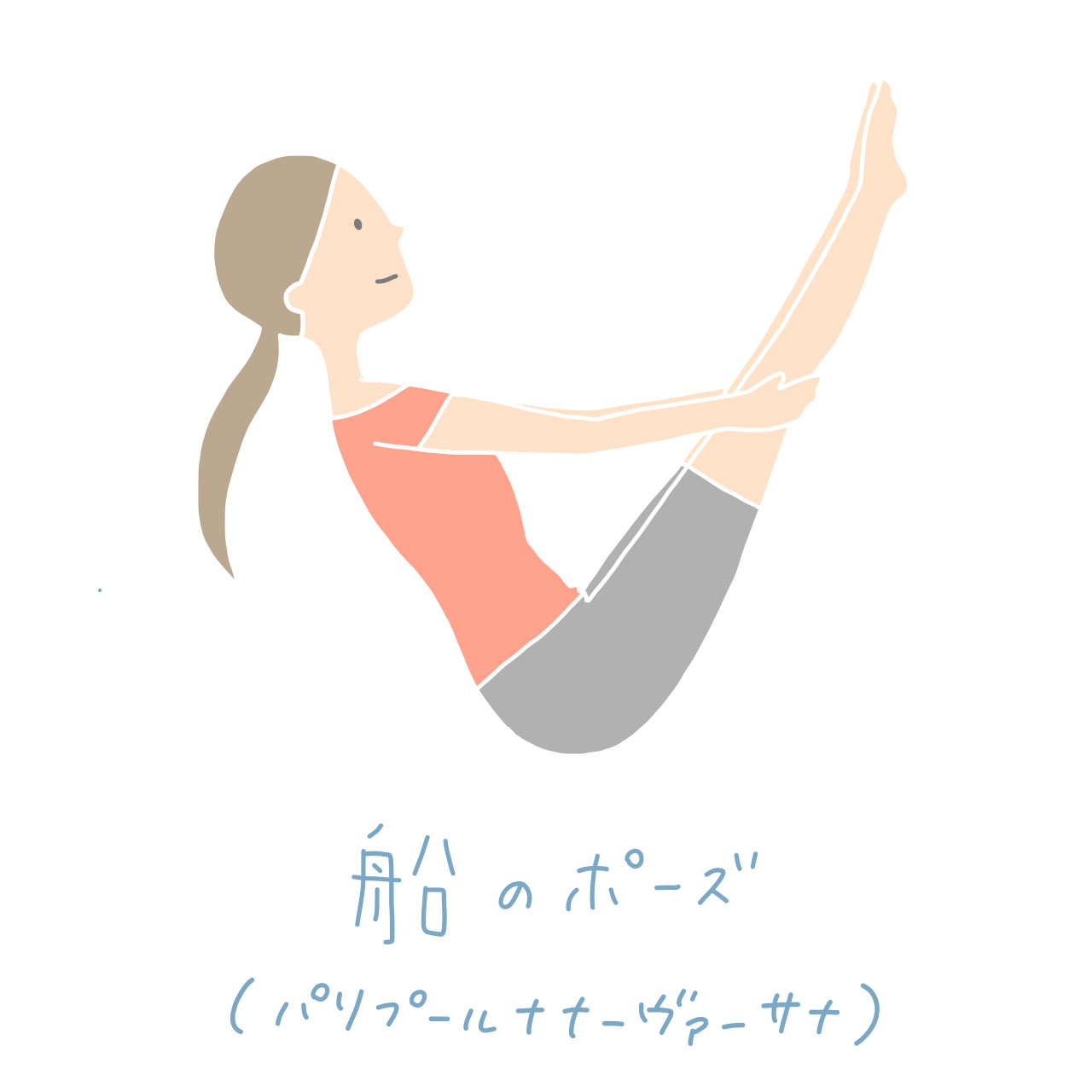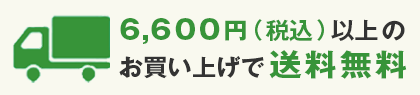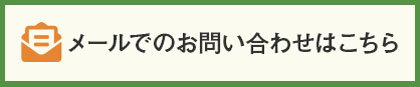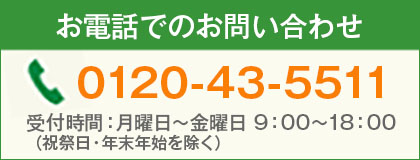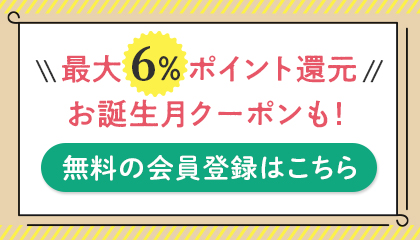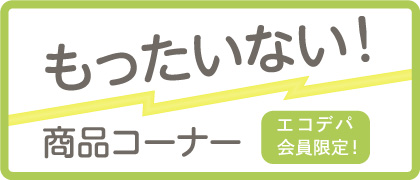こんにちは、エコデパスタッフの目代です。今週は先週に続き、新生活を迎える前にやっておきたい、心地よい暮らしのベースづくりについてご紹介します。今回は「防虫編」です。先週の「おそうじ編」も、ぜひ合わせてご覧ください。
>「【新生活を迎える前に】心地よい暮らしのベースづくりーおそうじ編ー」はこちら
お引越しや模様替えは、虫対策のチャンス!

家具や家電製品を動かすお引越しや模様替えは、暮らしの虫対策をするのに絶好の機会です。できれば家具を配置する前にお部屋全体の防虫をし、家具の配置の際には特に虫の棲家になりそうなポイントは重点的に対策を。
暮らしの中で出会う不快な虫の代表といえば台所害虫。さらにダニやコバエ、黒アリも人間にとっては困った害虫です。そんな害虫が出てきた時に、強い薬剤を使って殺虫してしまうのは簡単ですが、環境や人体への影響が気になります。
サスティナブルで心地よい暮らしづくりのためにも、できるだけ農薬成分には頼らずに、植物成分の力で虫を寄せ付けにくい空間を作りましょう。次に害虫の種類ごとにおすすめのアイテムをご紹介します。
できれば出会いたくない、台所害虫対策

冬の間、室内の家電製品の下などの暖かい場所で冬を越す台所害虫。お引越しや模様替えで、冷蔵庫や電子レンジを動かした時に出会ってしまった…という方もいらっしゃるのではないでしょうか。春になり、そろそろ台所害虫の活動が盛んになる季節でもあるので、しっかりと対策をはじめたいところです。
★台所害虫対策について、詳しくは以前にご紹介した「台所害虫に出会ってしまう前に、植物成分でしっかり対策を」をご覧ください。
一般的な台所害虫対策グッズといえば、集めて駆除するものや、現れた台所害虫にスプレーをして殺虫するものではないでしょうか。でもそれだと少なからず台所害虫の姿を見ることになります。
その点「忌避する=寄せ付けない、遠ざける」タイプの防虫グッズなら、台所害虫が棲みつきにくい空間を作るので、姿を見ることなく対策ができます。そのため台所害虫の姿を見ずに対策をしたい方は、安心して使うことができる成分で作られた忌避タイプの防虫剤がおすすめです。
ジェットタイプでお部屋全体を防虫空間に
青森ヒバ精油、植物油、ヒノキ蒸留水を配合した、ジェットタイプの防虫剤「ムシさんバイバイジェット」。お引越しの際や隠れた台所害虫が心配な時など、お部屋全体の防虫対策をしたい時におすすめです。
植物成分で室内空気汚染(揮発性有機化合物=VOC)の心配がないので、お子さんやペットと暮らすご家庭も安心です。
ワンルーム(6畳〜8畳)につき1缶を目安にお使いください。
スプレータイプで手軽に防虫!気になるところにシュッとひと吹き
青森ヒバやヒノキなどの植物由来成分でつくった「ムシさんバイバイ 防虫スプレー台所害虫用」。植物成分ながら忌避率はなんと約97%(チャバネゴキブリ)と頼もしい1本です。
流し回りやごみ箱、トイレなどのゴキブリの通り道となりそうな場所に定期的にスプレーしておくだけで、台所害虫が棲みつきにくい空間に。
スプレータイプで手軽に使えることや、防虫剤とは思えない青森ヒバの香りも人気のポイントです。ボトル約1.6本分でお得な「詰替用」もございます。
置き型で立てられるので、キッチンまわりの対策に!
害虫の通りそうな所、棲みつきそうな場所に置くだけ。30種類の樹木抽出成分(フィトンチッド)が空気中に発散することで、不快害虫が嫌がる空間を作り、その場に棲み付くことを防ぎます。ダニの増殖抑制効果も。
置き型で、効果は約2〜3ヶ月続くので、年間を通した対策としてもおすすめです。
置き型&スリム設計で、狭い隙間に潜む台所害虫に
薄さ約5mmの「ゴキシート すき間ブロック」は「ゴキのテキ」が入らないような、狭い隙間におすすめです。樹木抽出成分(フィトンチッド)が空気中に発散されることで、台所害虫が嫌がる空間(環境)をつくり、その場に棲みつくことを防ぎます。
忌避率約95%(チャバネゴキブリ)と効果抜群。効果は約2〜3ヶ月続き、お部屋の消臭にも役立ちます。
これからの季節気になる、ごみ箱のコバエに

気温が高くなると気になるのが、キッチンのごみ箱のニオイ、そしてコバエの発生です。そんなごみ箱には、防虫と消臭が同時にできるアイテムがおすすめです。
爽やかな香りでごみ箱内を消臭&コバエ対策
消臭効果の高い植物精油をブレンドすることにより、 ごみ箱内で混ざり合ったイヤなにおいも、効果的に中和・消臭します。 また、ごみ箱に寄り付くコバエ(ショウジョウバエ)をフィトンチッドの作用で忌避する効果も。
薄型のシートタイプで、両面テープで簡単にフタ裏に貼り付けられるので、邪魔になりません。 45Lのフタ付きゴミ箱に1個を目安に設置し、 月に1度交換してください。
次のページではダニ、黒アリ対策についてご紹介します。